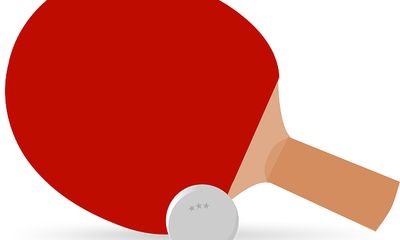小学校でも園でも、クラスの中には運動神経がいい子と苦手な子がいますよね。運動神経がずば抜けて良い子はたいてい人気者なので、「もしかしてうちの子、運動が苦手?」と感じているパパママは気が気ではないかもしれません。なにより、高校まで続く体育の授業が子どもにとってずっと苦痛なものとなったら、それはあまりにもかわいそうです。
でも、もし子どもが10歳未満なら改善の余地大!今回は、子どもの運動神経の改善方法についてお伝えします。



子どもの運動神経が悪いと感じる原因は?
運動が苦手な子どもを持っているパパママは、その原因を「遺伝」に求めがちです。でも、現代科学では「運動神経は遺伝しない」という考えが有力なのをご存じでしたか?
「もしかして、うちの子って運動音痴?」そう感じてしまう原因には、以下のようなものが考えられるようです。
【1】骨格や筋肉がまだ未発達である
成長過程にある子どもの筋肉や骨格はまだまだ未発達です。
子どもの成長は十人十色。周りの子より少々成長が遅くても焦らず、たとえ徒競走でビリをとってしまったとしても「最後まで頑張ったね!」と褒めてあげましょう。
「なんで早く走れないの」「他の子に比べると小さいねぇ」といった親からの心ない言葉がプレッシャーとなり、成長に悪影響を与えるケースもあるようです。
【2】脳からの指令がうまく伝わってない
身体は脳の指令によって動いています。初めて体験することより、慣れている作業の方がスムーズに行えるといった経験は、大人でも持っていると思います。そのため、運動経験が少なく、脳自体もまだ未発達な幼いうちは、指令の伝達が上手く行かず身体の動きがぎこちなくなると考えられます。
たとえば、走り出す時に手と足が一緒にでてしまったり、ジャンプのタイミングが合わず縄跳びが跳べないなど。でも、できるまで何度も繰り返していれば脳からの指令伝達が次第にスムーズになり、無意識にできるようになります。
【3】身体を動かす機会が少ない
【2】でも触れたように、運動で最も大切なのは「慣れ」です。身体を動かす機会が少ないと運動に身体が慣れず、結果として運動神経の発達も遅れてしまいます。
頭の良い子になってほしいから家で早期教育をする、危険だからと外遊びをさせないなど、親の期待による偏った暮らしをしていると、運動神経が良くなるどころか大人になってから健康を維持するための体力さえ身につきません。
現代の子どもはタダでさえ身体を動かす機会が減っています。心配や禁止ばかりせず、積極的に子どもに身体を動かす機会を与えてあげましょう。
運動神経を良くするために何ができる?
では、子どもの運動神経を良くするために何を大切にすれば良いのでしょう?
「ゴールデンエイジ」に運動を!
子どもには、運動神経を鍛えるのに最適な「ゴールデンエイジ」と呼ばれる時期があります。説により1〜2歳の差はありますが、大体3~15歳くらいまでの期間を指し、この間にどのような運動経験をしたかで生涯の運動能力、体力が決まると考えられています。このゴールデンエイジを逃さず運動体験をさせることが、子どもにとっては非常に重要です。
ゴールデンエイジはさらに3つの時期に分かれていて、それぞれで着目ポイントが異なってきます。
遊びや運動を通して基本的な身体機能を高める時期。この後に訪れるゴールデンエイジで飛躍的に運動神経を高めるために、特定の運動(スポーツ)に打ち込ませるより、いろいろな身体の動きを経験させることが重要です。この時期に同じ動きばかりを繰り返すと、身体の発達に偏りが出てきてしまいます。
さまざまな運動技能を瞬時に習得することができる、一生に一度だけ訪れる身体の黄金期です。プレゴールデンエイジ時代から身体を動かすことを習慣化し、運動に親しんでいれば、苦手だったことも突然できるようになったりすることも。運動神経が急成長し身体もしっかりとできあがっていきます。
神経系統ができあがる時期にさしかかるポストゴールデンエイジ。そのため、この時期からの飛躍的な成長を見込むのは難しいのですが、ゴールデンエイジ期に習得した運動の質を高めるのに最適とされています。
運動を楽しめる雰囲気作りを!
上記した通り、運動神経を良くするためには、適切な時期に経験を積むことが必要不可欠です。「運動することがつらい」と思ってしまうと、子どもは運動を嫌がってしまうため、いかに「運動が楽しい」と感じてもらうかが重要になってきます。
休日には家族そろってアスレチックのある公園で遊んだり、子どもの習い事で試合があったらみんなで応援したり、親が率先して楽しめる雰囲気作りに励みましょう。楽しむことができれば、子どもは意欲的に取り組みます。意欲的になれば結果的にたくさん身体を動かせるようになり、運動神経の向上に繋がります。
苦手意識を持ちやすい運動を一緒にやろう!
子どもが苦手意識を持っている運動は、パパやママが一緒に取り組むことで子どもの気持ちを前向きにすることができます。「今日は5回続くまでやってみよう!」など、少し頑張れば達成できる小さな目標をたくさん作って楽しみながら取り組みましょう。1つ1つの達成感を積み重ねていけば、きっと自信も生まれます。
ここでは、小学校の体育の授業でも必須の「鉄棒」「縄跳び」「マット運動」を例に、取組みのヒントをお伝えします。
◆鉄棒
鉄棒でとくに苦手な子どもが多い「さかあがり」。できなくても将来困りませんが、体育の授業ではできるまで特訓されたりするのでここはクリアしておきたい課題です。
・まずは、動画サイトでお手本となる動画を探して見せてみましょう。もちろんこれだけでできるようになるわけではありませんが、成功イメージを描きながらチャレンジできるので、案外重要なプロセスです。
・イメージを掴んだら、次はさかあがりのコツを掴みます。鉄棒の高さは「腰と胸の中間あたり」がベストな高さです。そして、「逆手ではなく順手」で鉄棒を持ち、「お腹を鉄棒から離さず、肘をまげて脇をしめる」。以上がさかあがりの基本姿勢です。
・基本姿勢をマスターしたら、斜めけんすいをして鉄棒に身体をひきつける体勢を保持できるようにしましょう。肘はまげて脇はしめ、へその辺りを鉄棒につけたまま、斜めけんすいの姿勢から上に向かって足を蹴り上げます。
全部をいっぺんに意識して練習するのは子どもには難しいです。少しずつ進んでいくような感覚で、根気強く練習をしましょう。
◆縄跳び
大人にしてみればただ縄を跳ぶだけの動作なのに、どうしてもできない子どもっていますよね。縄跳びができるようになるために大切なのは、ズバリ「リズム感」!縄に合わせるのではなく、跳ぶリズムに縄を合わせるのがポイントです。
まずは縄の長さをちょうど良く調節。次に一定のリズムを刻んだ手拍子に合わせて跳ぶ練習をしましょう。
押さえておきたいポイントは3つ。
- 着地する時は足全体ではなくかかとを意識
- 脇と肘をしめて縄を回す
- 前を見て跳ぶ
コツを掴めるようになるまで親子で気長に練習しましょう。縄跳びは意外にエネルギーを使います。パパママが先にバテないよう気を付けてくださいね。
◆マット運動
前転・後転・開脚前転など、練習が必要なマット運動。マット運動に大事なのは「恐怖心の克服」です。
・練習を始める前に、まずはしっかりと柔軟をしましょう。カラダガや若くなっていると成功率は上がります。怪我を防ぐ意味でもしっかりと!
・「前転」や「開脚前転」の場合は勢いよく前に転がることに慣れるのが大事です。最初は頭を布団につけたまま前に転がる練習をしましょう。
・それに慣れたら次は飛び込むようにしっかりと前転する練習です。勢いよく前転できるようになれば、開脚前転も練習次第でできるようになります。
・「後転」は、見えない後方に回るので、怖いと思うのは仕方ないことかもしれません。まずは、布団の下に傾斜をつけて、下り坂の勢いを借りて一気に回るようにします。その回転の感覚が掴めたら、次は傾斜を外して自分の力で回るようにしましょう。
親子で一緒に練習する場合は、まずパパやママがお手本を見せてあげるのも良いですね。家で練習する場合は布団の上で十分です。
子どもの可能性を信じて
運動神経の善し悪しは、どうしても周りの子と比較してしまいがち。でも成長のスピードは子どもそれぞれ。あくまで「今」できないのであって、ずっとできないわけではありません。練習を重ねればできるようになるはずです。
運動ぎらいにならないよう、子どものペースを尊重しつつ、その子だけの「ゴールデンエイジ」を大切にしてくださいね。
子どもの習い事を探すなら、コドモブースターを使おう!
子どもの習い事情報サイトも複数ある中でもコドモブースターがおすすめな理由はこれ!
近くの教室が検索・その場で体験予約ができる
習い事を探すとなったらやっぱり、家の近くの住所や最寄りの駅で探しますよね?
『コドモブースター』では、お住まいの地域や駅名などから近くの教室が検索でき、どんな習い事教室があるか一目でわかります!
またコドモブースター内で体験などの予約もできるのでとってもカンタン。
口コミで評判がわかる
気になる教室があっても、実際にはどうなんだろうと評判が気になりますよね?
周りに通っているお友だちがいなかったら、体験の1回で決めなければならないのは、ちょっと心配の方もいると思います。
『コドモブースター』では、教室の体験や入会された方の生の声を見ることができるので、教室選びの参考にもなりますよ。
おトクなキャンペーンも実施
時期によっては、アンケートに答えるとプレゼントがもらえるキャンペーンも実施しているので、とってもおトクです。



子どもの習い事を探すなら、まず『コドモブースター』で検索してみましょう!